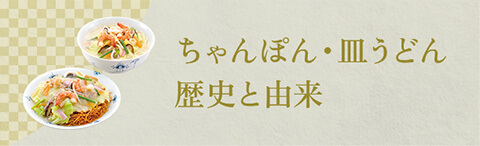第667号【癒しの唐比ハス園へ】
長崎県を含む九州北部地方の梅雨明けは、6月27日。梅雨入りは6月8日だったので、雨の季節は、わずか20日間でした。梅雨明け後は、夏空が広がり気温30度超えの真夏日が続いています。今年も全国的に厳しい暑さになるようですね。とにかく無理をせず、いつも以上に身体をいたわって過ごしたいものです。 暑さを忘れるほどの心安らぐ景色を求めて、唐比ハス園(諫早市森山町唐比西)へ行ってきました。諫早駅から「唐比車庫」行きの県営バスに乗って約35分。「水晶観音前」バス停下車。徒歩5分で、唐比湿地帯の一角に整備された唐比ハス園が見えてきます。 ハス園の広さは約2ヘクタール。ウッドデッキの通路を気持ち良く歩きながら10種類ほどのハスやスイレンの花を楽しみました。見頃は6月下旬から7月上旬だそうですが、8月に入ってから咲くタイプもあるとか。もうしばらく花を楽しめそうです。ところで、このハス園は、地元グループ「唐比すいれんの会」によって管理されています。ハス園の入り口に、唐比湿地帯の自然とハス園を守るための協力金を入れる黄色いポストがありました。感謝の気持ちを込めて200円。これからもこのハス園を楽しめますように。 ハス園を擁した唐比湿地帯の南側は、橘湾に面しています。もともとこの地は、海水の入る入江だったのが、約4000年前に淡水の湿地に変わったことが地層の調査でわかっています。地表から深さ11メートルくらいまでは、泥炭とよばれる地層が重なっているそうです。東側を望むと愛野展望台がある100メートルほど切り立った断崖が見えます。これは島原半島の成り立ちを知る手掛かりのひとつである千々石断層(ちぢわだんそう)です。この断層は唐比湿地帯まで続いています。唐比湿地帯が低地になっているのは、千々石断層の影響で沈み込んでいるからだそうです。 さて、このハス園での楽しみは、美しいハスやスイレンの花だけではありません。園内の用水路やハス池では、メダカやオタマジャクシなど、いろいろな水辺の生きものたちとの出会いもあります。オタマジャクシは、アマガエルのそれより数倍大きかったので、たぶんハス池に生息しているウシガエルの子なのでしょう。 きれいな池や川を好むというシオカラトンボをはじめ数種類のトンボも見かけました。そのなかに、日本でもっとも大きいトンボといわれる「オニヤンマ」によく似た「コオニヤンマ」もいました。小さなオニヤンマを意味するその名の通り、ややこぶりですが、黒と黄色の縞模様は同じで、見分けがつきにくい。明確な違いは、止まり方です。「コオニヤンマ」は胴体を水平にして止まりますが、「オニヤンマ」は枝などにぶらさがるような格好で止まります。 唐比ハス園一帯にはバン、ヒクイナ、セイタカシギなどの水辺の鳥が生息。珍しいヤツガシラが飛来することもあるそうです。今回見かけたのは、ホオジロ。ハス園内の樹木の枝先に止まり、胸を張ってしきりにさえずっていました。これは、繁殖期を迎えたオスの特徴だそうです。 自然豊かな唐比ハス園一帯は、その地形や地層に、ダイナミックな地球の鼓動を感じたり、多種多彩な生きものたちとの出会いを楽しめるネイチャースポットです。この夏、お子さんと一緒に出かけてみませんか。
もっと読む