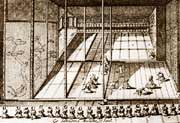第42号【気分爽快、長崎港クルージング!】
気象庁の梅雨入り宣言直後に訪れた"梅雨の晴れ間"。お天気が良いのはうれしい事ですが、どうしていつもこうなの?と雨の季節への心構えをくじかれたようでちょっとプリプリ…。それはそうと、私にはやるべき事がある!そう、「長崎港クルージング」。さっそく、行ってまいりましたよ~。┌(^0^)┘GO!GO! ところで「クルージング」というと、船でさっそうと大海原を駆けめぐるというイメージが浮かびますが、今回のは少し違います。深く入り組んだ長崎港の一番奥から、港の沖合(出入口付近)までを海岸線をたどるように60分かけて1周するもので、遊覧船でゆっくり港を巡るのです。(⌒▽⌒)/ノンビリイコウ! 船の発着場所の大波止ターミナルからは、「やまさ海運」、「安田産業汽船」という2つの船会社が長崎港めぐりの定期便を出しています。いずれもルートが似ていて、所要時間も同じ(料金は違います)。両方の便を合わせると朝から夕方までの間に約10本は出ています。(‘▽’)利用しやすい! さてターミナルの窓口で大人料金1200円を支払い、朝10時45分発の船(安田産業汽船)が待つ桟橋へ。「ゼリーフィッシュ(くらげ)」というユニークな名を持つ遊覧船に乗り込むと、すでに約30名ほどの乗客が思い思いにくつろぎ、出航を待っていました。軽食やドリンク類が楽しめる船内は、1階が窓越しに展望を楽しめるスペース、2階は360度に視界が広がる屋根付きの広いデッキ。この日はお天気が良かったので皆2階へ。さあ、初夏の爽やかな風を感じながら、いよいよ出航です。(^〇^〃)ゞワクワク▲可愛い?カラーリングでひときわ目立っていたゼリーフィッシュ コースを簡単にたどってみましょう。まず三菱重工長崎造船所へ。巨大な工場をかなり近距離で見る事ができます。ほどなくして数年後に完成が予定されている女神大橋の架橋場所が見えて来ました。この橋は新しい観光スポットとして期待されています。次にキリシタン殉教にまつわる「高鉾島(たかほこじま)」、続いて昔、長崎市民が海水浴場として利用していた「ねずみ島」。▲すれ違う船に子供達も大喜びそして大浦天主堂の次に古い「神ノ島教会」と海に向かって立つ「マリア観音像」。ここで長崎港の沖合に浮かぶ伊王島、高島を望みつつUターン。三菱重工の「100万トンドッグ」、グラバーさんが明治元年に創業した「ソロバンドッグ」、異国情緒あふれる建物が目を引く「南山手の景観」と続いて終点です。▲神の島教会と船舶の安全を祈願して建立されたマリア観音像 船内では出港時からアナウンスで丁寧な解説があります。長崎の港にまつわる話をいろいろ聞けて得した気分になりますよ。それにしても、いつもと違う視点で見る長崎は格別の味わいでした。かつて長崎港へやって来た異人さんたちはその美しさを褒め讃えたそうです。時代を経てずいぶんその姿も変わったのでしょうが、何だかその気持ちがわかるような美しさでしたよ。(☆☆)行って、良かったァ
もっと読む