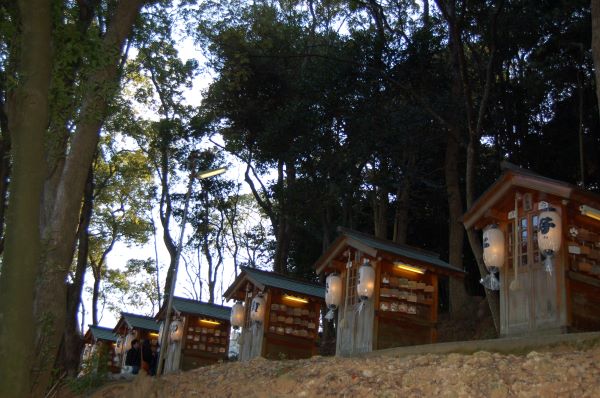第400号【長崎の春2012】
先週、満開を迎えた長崎の桜。八分咲きの頃に春の大嵐に見舞われましたが、よく耐えました。嵐が過ぎ去った翌日、桜の名所として知られる風頭公園へ足を運ぶと、大勢の人々が桜の樹の下でお弁当をひろげていました。東北や北海道の桜の見頃はゴールデンウィーク前後でしょうか。長崎は早くも葉桜の季節へ移りはじめました。山の緑も日に日に濃くなっています。 春もたけなわのこの季節、江戸時代から続く長崎の風物詩といえば「ハタ揚げ」です。ハタ揚げの日ともなると前日の夜から参加者が会場となる山の頂きに集まり、たいへんな賑わいだったと伝えられています。江戸時代の風俗を描いた長崎名勝図絵にもその様子は描かれていて、当時の熱狂ぶりが伺えます。 現代の「ハタ揚げ」はというと、やはり相変わらずの人気ぶり。毎年4月はじめ頃に開催される地元新聞社主催のハタ揚げ大会では、世代を問わず大勢の市民が集います。会場は長崎港と市街地を見渡す景勝地「唐八景」の山頂。かつて「ハタ揚げ」はもっぱら男子がするものでしたが、いまでは女性の姿も大勢見かけます。 ただ、「ハタ合戦」となると、やはり男の世界です。手元での巧みなヨマ(ハタを揚げる糸)さばきで、遠く上空にのぼったハタを操縦。空中で相手のハタに交差させ「ビードロヨマ」(粉状に砕いたビードロを塗った糸)で相手のハタを切り落とすのです。大勢の観客が手をかざしながら勝負を見守っていました。 「子供の頃は、みんな自分でハタを作って揚げていた」と話す地元の80代の男性は、ハタの骨組み(縦骨1本と横骨1本を十字に交差させたシンプルな構造)となる竹の弾力や、よまの付け具合など自分なりに工夫する楽しみがあり、ハタを揚げるときには風を読んだり、技を競い合ったりするところが面白いといいます。 また、70代の男性は、「ハタ揚げは男のロマン」と言います。「子供の頃、しつけに厳しかった祖父はお小遣いをくれない人だったけど、ハタを買うと言うと快く出してくれたものです」。 ところで、男子がハタ揚げに興じるそばで、ワラビ摘みに夢中になっている女性がいました。声をかけると、「灰汁抜きは面倒だけど、おいしいものね」と照れ笑い。そう、いつだって女性は現実的なのです。 ハタ揚げ見物を終え、土の感触を楽しみながら山道を歩けば、土手にツワブキがいっぱい生えていました。長崎では「ツワ」と呼ばれ、煮しめや味噌漬けなどにして食べます。そして、足下に目をやれば、スミレやジロボウエンゴサク、オキザリス、オドリコソウなど野山の小さな花たちが元気に花を咲かせていました。さあ、次の休日はお弁当を持って春を散策しませんか。ツワブキジロボウエンゴサクオキザリス オドリコソウ
もっと読む