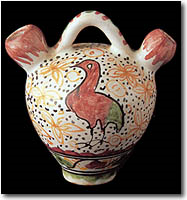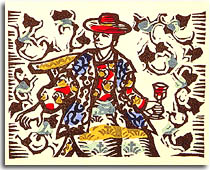第513号【師走、ちゃんぽんを食べながら】
師走半ば五島在住の方から、かんころもちが届きました。お礼の電話を入れると、「高齢なので、かんころもち作りはあと数年で引退かも…」とポツリ。5月、サツマイモの苗植えからはじまるかんころもち。秋の収穫やイモを蒸して干す作業も体力勝負で、家族や友人の「おいしかったよ」の声を励みに毎年作っているそうです。我が家では、かんころもちはすっかり師走の風物詩。届くと先方のお元気そうな様子が見えてきて、ほっとします。今年もありがたくいただきました。 何かと忙しい年末ですが、恒例の贈り物が届いたり、帰省した親戚の子や友人たちが、ひょっこり訪ねてくるとうれしいものです。久しぶりの顔ぶれが揃うとき、我が家では地元産の牡蠣などいつもよりちょっと贅沢な具材を使ったちゃんぽんで、もてなします。ちゃんぽんは、「おいしい」と喜ばれるのはもちろんですが、作る側にとっては手間がかからないので、ありがたい。手前味噌になりますが、麺もスープもやっぱり「みろくや」。試作と研究を重ねた絶妙な加減で、野菜やお肉、魚介類のおいしさを引き立てます。 お客さま用に加え、年越しそばならぬ、年越しちゃんぽん用など、年末年始はちょっと多めにちゃんぽん麺とスープを買い置きします。そのお買い物がてら眼鏡橋界隈へ出向くと、冬休みとあって若者の姿が多くみられました。護岸の一角にはめ込まれたハート・ストーンは、すっかり恋する人たちのパワースポットに。眼鏡橋の2つのアーチがくっきりと水面に映る光景が見られる、ひとつ下流にかかる袋橋には写真を撮る人が次々にやって来ます。この界隈で最近目立つのは、中国からの観光客です。ところで彼らは、眼鏡橋をはじめとする中島川の石橋群が、中国にゆかりのあることを知っているのでしょうか。 中島川にかかる眼鏡橋は、寛永11年(1634)、唐寺・興福寺の二代目住職で黙子如定という唐僧が浄財で架けた橋です。これを機に当時、長崎に居住していた中国人貿易商らの寄附により、中島川に次々に石橋が架けられました。石橋は、木の橋と違って洪水のたびに流されたり、腐ったりしません。当時、長崎港に入った唐船はその荷を小舟に移し、中島川上流の桃渓橋あたりまで漕いで来たそうなので、荷を上げ下ろしするためにも丈夫な石橋は必要だったのかもしれません。また、多額の寄附は、長崎を拠点にした商いで富豪となった彼らの恩返しであり、このまちに溶け込もうとした気持ちの表れであったかもしれません。いずれにしても、彼らがその財力を石橋にそそぎ、長崎のまちづくりに活かしたことは大きな意義のあることでした。 中島川の石橋群だけでなく、長崎には中国とゆかりのある場所がそこかしこにあり、興味をそそる謎めいたことも多々あります。たとえば、長崎市鳴滝地区にある唐通事の彭城(サカキ)家の別宅跡(現・県立鳴滝高校)。江戸時代、その庭園の一隅に置かれていたという陶製の織部灯篭(復元)がいまも残されています。十字のデザインが配され、別名キリシタン灯篭ともよばれるものを、禁教時代になぜ彭城家がもっていたのか。その真相は知る術もなく、謎が謎を呼ぶばかりです。 しかし、歴史の真相はわからないから面白いもの。長崎と中国の友好の証しでもあるちゃんぽんを食べ、ああだ、こうだといいながら、来年もその迷宮を右往左往して楽しみたいと思います。今年も読んでいただき、誠にありがとうございました。
もっと読む